現在、建築の世界では3D図は当たり前となってきた。工務店やハウスメーカーでさえ3D図を作ってお客さんにプレゼンをする。やはり競争の世界なので、他社がやっていたらせなイカンという事だろう。だがそのデザインが売りである設計事務所などでは3Dも作るが、3Dはあくまで図面集の表紙的な『絵』として捉えているところが多いようだ。というのも3Dはお客さんの目を引くのは確かだが、やはり出来上がりとは質感の違いやボリュームの違いがでやすいし、その太陽光の加減でも見栄えは違ってくる。なので設計事務所の場合は大抵の場合模型を作る事が多い気がする。
と言っても作る模型はプレゼン用であり、また設計する者のためにあである。決してお客さんである施主さんにプレゼントするための模型ではない。なので別にこった作りの物ではなく、スチレンボードが足りなくなったので、『愛媛みかん』と書いてある段ボールを使った事すらある。いわゆるスタディー模型と呼ばれる物である。スタディー模型とは設計を行う際にボリューム感や周辺の家々との兼ね合いを確認するための簡易的な模型の事だ。大建築家と呼ばれる人々でも、頭の中で考えていた空間を実際に作ると想像していたカタチと異なる事がよくある。なので模型を作る事でその空間的な間違いを修正すために作る。また3Dをプリントアウトした2Dの図面よりも説明がし安く、またがんばった感があるので家主さんにもお見せしたり、それを写真に取り込んでプレゼンをしたりする。通常は白いスチレンボードを使い、格段色は塗らない。というのも、色が塗ってあると一般の方々はそちらの方に目が行きやすく、結局はボリューム感などの判断が難しいからである。
今日の夕方、とある知り合いの方に図面チェックを依頼され合ってきた。大手のハウスメーカーさんとプランを練っているのだが、第三者としての意見が欲しいという事である。さすがハウスメーカーさん、素敵なキラキラとした3Dを作ってらっしゃった。ハウスメーカーさんには3Dを作る専門の職員がいるので出来る仕事ではある。『実際はどんな感じでしょうか?』と奥さんに聞かれたので『模型を作るとすぐ分る』と答えた。相手がハウスメーカーさんだが、同業者の立場、図面や3Dを書く苦労はよく分る。よってむげに否定はできないからだ。その後雑談となり、奥さんが、『よく新聞で建築模型士講座みたいなのやっているけど、あれってどうなんですか?』と言われた。
よく新聞で『建築模型士講座を通信教育で!』みたいな募集をやっている。調べてみると、自宅で3万から6万は稼げるみたいなことが書いてある。まあ確かにスタディー模型ではなく、本物の気合いが入った模型であれば、材料代や諸経費、それに作業量に対して時給換算すればそのくらいは安い物だ。だが需要は限りなく少ないと言えるだろう。僕が住む宮崎で自宅で模型を作って稼いでいる主婦がいるかと言えば、まずいない気がする。まず設計事務所自体が本気の模型を外注するほど儲かる仕事ではないし、ハウスメーカーさんや工務店で模型を作る事自体の発想はまずない。あるとすればマンションの展示会場の模型であったり、博物館などの模型であったりする。だがそれらは大手の模型屋が作る100万以上のアクリルの模型であり、主婦が片手間で作れるほどの模型ではないし、そんな設備を持つ主婦はまずいないであろう。ただ、この通信教育は人を騙しているという人もいるが、この通信教育は5万ちょいぐらいの金額であり、模型を作る楽しみを覚えるという感覚なら良いかも知れないとは思う。通信教育を終了し、設計事務所などにスタディー模型を作らせて下さいと営業すれば、少しは作らせてくれるかも知れないが、どうだろう。。
僕が勤めていた京都の設計事務所の大先生は、とある京都の良い香りのする女子短大で建築についての講義をやっていて、僕はその助手をやっていた時期がある。大先生がお話しし、僕は主にEnterを押すのがお仕事だ。ある日、大先生が北海道に行ってしまったため、僕が教えるハメになった。しょうがないので、その日は模型と建築についての講義をしてあげた。僕が作った『愛媛みかん』葺きの屋根がキラリと光っていた。
今日の夕方、とある知り合いの方に図面チェックを依頼され合ってきた。大手のハウスメーカーさんとプランを練っているのだが、第三者としての意見が欲しいという事である。さすがハウスメーカーさん、素敵なキラキラとした3Dを作ってらっしゃった。ハウスメーカーさんには3Dを作る専門の職員がいるので出来る仕事ではある。『実際はどんな感じでしょうか?』と奥さんに聞かれたので『模型を作るとすぐ分る』と答えた。相手がハウスメーカーさんだが、同業者の立場、図面や3Dを書く苦労はよく分る。よってむげに否定はできないからだ。その後雑談となり、奥さんが、『よく新聞で建築模型士講座みたいなのやっているけど、あれってどうなんですか?』と言われた。
よく新聞で『建築模型士講座を通信教育で!』みたいな募集をやっている。調べてみると、自宅で3万から6万は稼げるみたいなことが書いてある。まあ確かにスタディー模型ではなく、本物の気合いが入った模型であれば、材料代や諸経費、それに作業量に対して時給換算すればそのくらいは安い物だ。だが需要は限りなく少ないと言えるだろう。僕が住む宮崎で自宅で模型を作って稼いでいる主婦がいるかと言えば、まずいない気がする。まず設計事務所自体が本気の模型を外注するほど儲かる仕事ではないし、ハウスメーカーさんや工務店で模型を作る事自体の発想はまずない。あるとすればマンションの展示会場の模型であったり、博物館などの模型であったりする。だがそれらは大手の模型屋が作る100万以上のアクリルの模型であり、主婦が片手間で作れるほどの模型ではないし、そんな設備を持つ主婦はまずいないであろう。ただ、この通信教育は人を騙しているという人もいるが、この通信教育は5万ちょいぐらいの金額であり、模型を作る楽しみを覚えるという感覚なら良いかも知れないとは思う。通信教育を終了し、設計事務所などにスタディー模型を作らせて下さいと営業すれば、少しは作らせてくれるかも知れないが、どうだろう。。
僕が勤めていた京都の設計事務所の大先生は、とある京都の良い香りのする女子短大で建築についての講義をやっていて、僕はその助手をやっていた時期がある。大先生がお話しし、僕は主にEnterを押すのがお仕事だ。ある日、大先生が北海道に行ってしまったため、僕が教えるハメになった。しょうがないので、その日は模型と建築についての講義をしてあげた。僕が作った『愛媛みかん』葺きの屋根がキラリと光っていた。





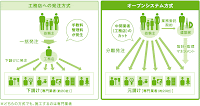









.jpg)






- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact